180万膳のストーリー
箸はどのようにして生まれるのか
木箸職人・山田政義さんの仕事場に通うようになってから早十数年。今でも「銀座夏野」に新しいスタッフが変わるとそのスタッフを引き連れ、研修を兼ねつつ、山田さんのもとを訪れています。
一膳の箸がどのようにして生まれるのか。
一流の職人がどのようにして箸づくりと向き合っているのか。山田さんの工場を訪うことは、木箸作りの伝統を今日に受け継ぐ仕事ぶりに、間近で接することのできるまたとない機会を得るということです。今回は本書の取材ということもあり、山田さんに無理を言って箸作りの一連の流れを、一足飛びで見せていただくことにしました。
いつ訪れても、 箸一膳が完成するまでにこれだけの“手”がかかっているのか、と感心させることしきりです。
箸職人、ひと筋五十年
ではまず、簡単に山田さんの紹介から。先代までは東京に工房を構え、山田さんの代になってから埼玉県児玉郡美里町で、現在の「山田箸製作所」を開かれました。
「父親も母親も箸の職人でしたが、父親は何も教えてくれませんでしたね。まぁ、いわゆる“見て覚えろ“という昔気質の人でした」と話してくださった山田さんは、1944年の生まれで現在は70歳。この道50年と言う箸一筋の職人です。
「若いころなら一日1,500膳ぐらいつくれていたけど、今は昔と違って工程も増えだから、昔の3分の2もいかないかなぁ。まぁ平均すると、年々35,000~36,000膳というところでしょうか。」
山田さんはこんなふうに、こともなげに語ってはいたものの、少なく見積もっても36,000膳×50年で、これまでにざっと180万膳を手がけてきた計算になります。
腕の良い職人は仕事が速いー。
これからこれは今も昔も変わらないと思います。
山田さんの仕事をはたで見ていると、その動きは実に小気味よく、リズミカルです。
そして作業が興に乗ってくると、無駄な動きが一切なくなり、そのスピードはいったいどこまで速くなるんだろう、と感じてしまうなるほどです。
丸太を挽くことから始まる
山田さんの箸作りの特徴の一つは「丸太から始まる」こと。

普通は「大割り」と呼ばれる板状に製材されたものだったり、あらかた箸の形状になっている「小割り」と呼ばれる材料だったりから箸作りを行うことが多いようです。簡単に言うと、仕上げだけ行う箸職人が多いということです。
ところが山田さんは、丸太を挽いてまずはブロック状にし、さらにそこからブロックを挽いて板(大割り)にしていきます。
丸太から始め、大割りを作るところからこなす職人は、全国的にみても数少ない存在です。

「前に飛びますから気をつけてください」
と言って山田さんが挽きはじめたのは「青黒檀」という極上の材料。
実は箸の世界では最近、「いい“アオコク“がなかなか手にはいらない」と言われるほどの、特別な木です。
ただし、厳密には「小割りになった“いいアオコク“がない」だけで、山田さんのように丸太から仕入れ、木目などを見ながら箸に適した材に挽く技術があれば、みごとに青黒檀の箸を作れるのです。
木の中の、水の流れを読む
次に山田さんが挽きはじめたのは「斧折樺(オノオレカンバ)」という木。「小割り」の作業の開始です。
傍目には次から次へ、淡々と材を挽いているようにしか見えません。けれども山田さんは、時折材の向きを変えたりしながら、“何か“を素早く判断しつつ挽いていました。
山田さんの手が止まった時を見計らって、わたしは「木目ですか?」と尋ねました。

「ですね。後は道管です」と山田さんは答えました。
道管とは、正確には「被子植物の維菅束の木部を構成する組織」のことですが、平たく言うと、根から吸収した水や養分を上部に送るための管のことです。
挽いた材を見ると、木目とは別に線が走っています。この道管が将来的に、箸の「折れる・折れない」「反る・反らない」へとつながります。
「こっちへこう木目が走っているでしょ。で、道管はこっちへこう走っている。こっから先が細くなっていて、ここから先は太くなっていてーー」
と、山田さんはこの材をどう挽くべきなのかを、丁寧に説明してくれました。 私たちは一つひとつの線をじっくり目で追いながら、ふむふむと聞いていたけれど、山田さんは毎分3,500回転もする刃と数ミリの距離で対峙し、木目にも、道管にも、瞬時のうちに目を配り、滞ることなく、木を刃に送り込んでいるのです。

山田さんがこの世界に入ったのは16歳の時。
製材を始めたのは20歳を過ぎてからだそうです。
山田さんは作業を続けながら、淡々とこうおっしゃいました。
「木は全部、違いますから」
手仕事らしい、温かみのあるフォルム
「大割り」「小割り」の次はサンドペーパーで「削り」の作業が始まります。
この工程は箸をつくる作業で、グラインダーという機械を使い一本ずつ削りながら成型します。
持ち手の形状は四角形(胴張)、五角形、六角形とさまざま。繊細な箸先も含めて、山田さんは何角形だろうと、どんな形状だろうと、培った感覚を頼りに形をつくりあげていきます。

削り終わった箸を手にとると、手仕事らしい、温かみのあるフォルムを感じ取ることができます。次に、「ガラ掛け」と呼ばれる、箸の表面を全体的に滑らかにするための工程に入ります。これは基本的に塗りの仕上げなどを行わない木箸作りの、大きな特徴のひとつです。
簡単な機械を使って水と砂で研磨していくものですが、この「ガラ掛け」のおかげで、表面は気持ちいいほどつるつるに仕上がります。
太陽の力も借りて
「ガラ掛け」が終わると天日干しを行います。工場の屋根が箸を干す場所になっていて、屋根一面に6,000膳もの箸がずらりと並びます。
この天日干しは「乾かす」ことが目的というより、「選別」が主たる目的のようです。
山田さん曰く「この段階で曲が出ている箸は、すべてはじきます。
特に天気の良い、カンカン照りの日なんかは、曲がりが出る箸はすごく曲がる。そんな箸は商品になりませんから」とのこと。
大量生産のまるで工業製品のごとき箸は、機械で一気に強制的に乾かすその一方で、山田さんはお日さまの力を借り、時間をかけて乾かし、素材としての良し悪しを自分の目で一つひとつ確認する。
木を挽いているとき、「木を見る」ことがある種、職人の大切な仕事のひとつでしたが、天日干しにおいても「木を見る」ことはとても大事な行為となるんです。
山田さんの木と向き合う姿勢は、いつも、本当に誠実です。

木そのもので、勝負する
最後の仕上げは「バフ掛け」です。漆上げの場合また別の工程が控えていますが、この日は昔ながらの木箸らしい生地の箸を手がけていたので、天然由来のカルナバワックスを使って磨き上げていきました。
木箸の特徴は何といっても、塗りなどの“加飾“をせず、木地そのもので勝負することです。だからこそ、木そのものが重要ですし、フォルムや手触りはごまかしがききません。ある意味、つくり手の技量と志がストレートに表れる箸だと思っています。木片は物語る工場の裏には、残念ながら箸になれなかった木片が、寒い日のストーブの薪としてうず高く積まれています。なかには銘木と呼ばれるような木片すら、無造作に転がっています。
その木片の山を見るにつけ、今手にしている箸のありがたみをひしひしと感じます。
180万分の一膳ですらおろそかにしない、山田さんの木箸職人としての気高き姿勢は、箸足り得なかったそれらの木片たちが、 密かに物語っているような気がします。

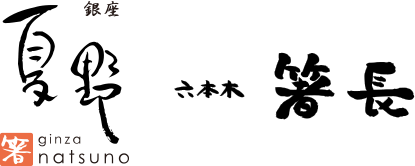

 ログイン
ログイン カート
カート お気に入り
お気に入り